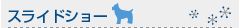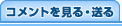このような記事が目にとまりました。
聴診記「同伴者としてのペット」〜西日本新聞6/1朝刊

九州にもゆかりのある作家遠藤周作(1923〜96)は37歳から38歳にかけて、肺結核の再発により3度の手術を受けている。6時間に及んだ3度目は、心臓が一時停止するほど危険なものだった。病室に戻ると、誰にも言えない不安や孤独を打ち明けてきた九官鳥が身代わりのように死んでいた。
遠藤はこの体験を、幾つかの短編と最後の長編小説「深い河」に投影させている。短編「男と九官鳥」では、息子夫婦に見放されて病院へ送り込まれた老人が亡くなったあと、残された九官鳥が老人の声で「カア、ちやん」と鳴く。肺を患った孤独な老人は、先に逝った女房に、あるいはずっと前に亡くなった母親に、何かを訴えていた。いつも傍らにいた九官鳥がそれを覚えていたというのである。遠藤文学の九官鳥を思い出したのは、長崎にお住まいの30代の女性から、大切なペットが死んで悲しみに暮れているというお手紙を頂いたからだ。ロサンゼルスに住んでいたとき知人にもらったマリモという名の猫は、女性とともに16年生きた。帰国したとき。結婚したとき。初めての子が亡くなったとき。続く4人の子が生まれたとき。離婚したとき・・・。5月6日の未明に息途絶える前、吐血したマリモは女性のひざに乗ってきた。その体は血と尿で汚れており、死が近いことを悟った女性は「マリ、今までありがとうね。大好きだよ」と声を掛け、ぬくもりを確かめたという。
遠藤が描く猫や犬や鳥は同伴者としてのイエス・キリストを暗示しているのだが「彼自身の人生のなかで、犬や鳥やその他の生きものが、どんなに彼を支えてくれたかを感じた」という「深い河」の記述など、素直に共感する人は多いのではないか。ホスピス医療の現場でもペットの存在は見直されつつある。
マリモが死んだ夜、パソコンに向かっていた女性は、隣りの部屋でマリモが床に飛び降りる音を聞いたという。小学生の長男は、夜中に廊下を歩くマリモの足音がしたといい、次男も、寝ているときに布団に乗ってくるマリモの鼻息が聞こえた、と言ったそうだ。
一家にとってマリモもまた、生と死を超えた同伴者だったということだろう。
(編集委員・田川大介)

 ジョンちゃんのMY ROOM
ジョンちゃんのMY ROOM